概要
『琵琶記』(びわき)は、中国元末から明初にかけて活躍した高明が著した元曲の代表作です。
全42幕からなる戯曲(ぎきょく)で、科挙合格のために都へ上京した蔡伯喈(さいはくけつ)と、その妻・趙五娘(ちょうごじょう)が別離と再会を経て結ばれる物語を描いています。
歴史的背景
高明は元の至正5年(1345年)に進士となるも、国内の混乱を避けて疎開しました。
彼がもとにした原作は宋代で伝わった雑劇『趙茜女蔡二郎』とされ、その筋書きを元曲の形式に改編したと伝わっています。
元末から明初の社会不安や文化復興の機運を背景に、『琵琶記』は道徳的な教訓と夫婦愛を主題に据えた優れた作品として重視されました。
文化的背景
舞台では琵琶の伴奏が用いられ、楽器に託した感情表現が重要視されました。
『琵琶記』という題名も、五娘が琵琶を携えて夫を探す象徴的な場面に由来し、中国伝統音楽のなかで琵琶が果たす役割を強調しています。
主な登場人物
・蔡伯喈(さいはくけつ)・・・男性主人公。科挙受験のため上京し、変転の末に五娘と再会する官吏。
・蔡公(さいこう)・・・伯喈の父。伯喈を上京させる。
・蔡母(さいぼ)・・・伯喈の母。子を慕い心配する。
・趙五娘(ちょうごじょう)・・・女性主人公。母とともに苦難を乗り越え、琵琶を携えて夫を捜す。
・張太公(ちょうたいこう)・・・蔡家の隣に住む老婦人。五娘を支える隣人。
・牛太師(ぎゅうたいし)・・・再婚先で五娘に冷遇を強いる官吏。
・牛氏(ぎゅうし)・・・太師の娘。
・李華(りか)・・・太師家の下男。
著書の内容
科挙合格を志す蔡伯喈は父の命を受け、妻・五娘と涙の別れを交わします。
都へ向かう道中には、親戚や門弟たちによる励ましと、再会を誓う言葉が台詞と曲調で重ねられます。
試験直前、伯喈は母の病気を理由に一時帰郷を願い出ますが、官吏の命令で許されず、逆に失格の危機に陥ります。
父・蔡公から「科挙を最後まで戦い抜け」と叱責される場面では、伯喈の揺れる葛藤が琵琶の伴奏とともに表現されます。
官府からの急使が到来し、五娘への別離を告げる勅令を読み上げるシーンは、儒教的な忠孝二律背反を鮮明に描き、南曲ならではの抒情的な掛け合いで緊張感を高めています。
都に残された五娘は、姑や隣人から「科挙に縋る身勝手な女」と厳しく非難されます。
家計を支えるため、素手で壺を掘る逸話や、食を絶たれた場面では彼女の貞節と忍従が対比的に描かれます。
やがて五娘は琵琶を携え、街頭や門前で弾き語りを始めます。
西廂の名場面を模した琵琶独奏では、旋律を通して内面の嘆きを観客に訴え、同時に物乞いに赴く姿で貧窮の深刻さを表現しています。
生活が行き詰まると、髪を売って衣を得る場面が登場します。
ここでは五娘自らの髪が琵琶と同じく「音楽的モチーフ」として機能し、身体の一部すらも犠牲にして夫を待ち続ける強さを象徴しています。
五娘は再婚を強いられ、冷酷な牛太師の家に入ります。
姑や義姉たちの陰湿な嫌がらせに加え、屋敷から追い出されるシーンでは群舞が用いられ、集団による圧迫感を舞台上で演出します。
逃亡した五娘は道教尼庵に身を寄せ、仏道に帰依。
尼僧たちと琵琶を共鳴させつつ、儀式的な歌唱で過去の涙を浄化する場面は、元曲が宗教儀礼とどう融合するかを示す重要な転換点です。
やがて都への巡礼路でかつての曲を奏でながら旅する五娘。
道中の男声コーラスと合流し、夫への想いが集団的な祈祷へと発展していきます。
都で官職に就いた伯喈は、役所の廊下から聞こえる五娘の琵琶に足を止められます。
旋律が特定の節を経るごとに、二人の思い出が舞台上に重ねられ、最終的に伯喈が「この音曲は我が妻のみ知るもの」と叫ぶクライマックスを迎えます。
認識劇には、錦衣宰相や父母、曾て別れを告げた官吏たちが次々に登場。
五娘の貞節を讃える群集劇で物語は頂点に達し、最後は一家団欒の祝宴へ。
琵琶の和声と全登場人物による合唱で大団円を迎えます。
この詳細な物語展開を授業に取り入れる際は、各場面における音楽と演劇技法の結びつきを解説すると、南曲の魅力がより深く伝わります。
まとめ
『琵琶記』は、元曲の中でも情感豊かな旋律と緻密なセルフ構成を伴った傑作とされています。
原作の宋代雑劇から受け継いだ夫婦愛と倫理観、そして琵琶という楽器を媒介にした象徴的表現は、後世の演劇や小説にも影響を与えました。
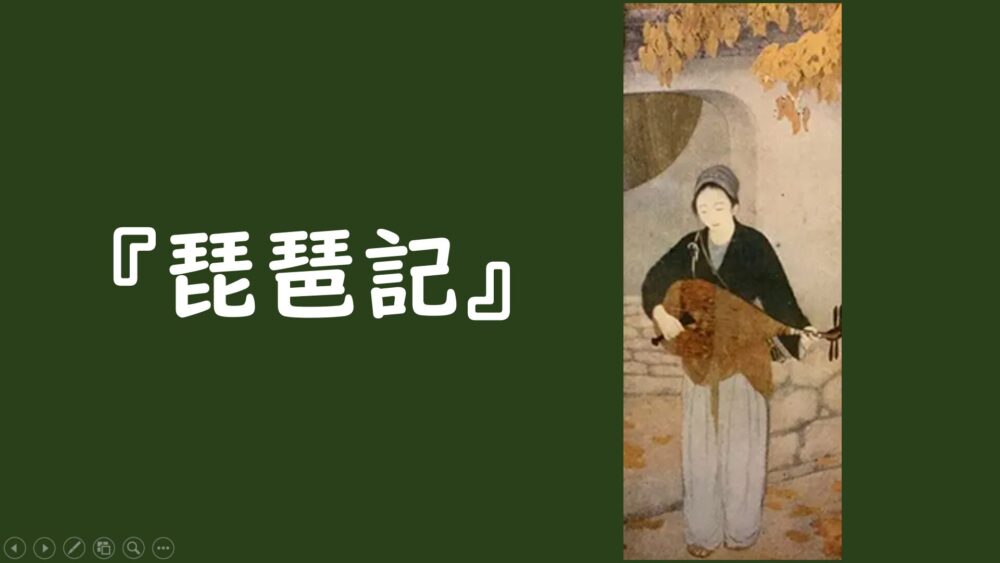
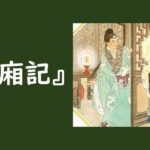
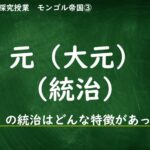
コメント