概要
『西廂記』(せいしょうき)は、元代末期に成立した元曲です。
故事小説をもとに、若い書生・張生(ちょうせい)と名門の令嬢・崔鶯鶯(さいおうおう)の悲恋を描きます。
全五折(まれに四折)の長い芝居で、恋愛に悩みながらも詩や歌で互いの心を確かめ合う情景が魅力です。
歴史的背景
元末期、中国はモンゴル支配の下で社会が大きく揺れ動いていました。
書生や狭き門となった科挙の受験生の旅費は苦しく、地方から都へ学問を求めて上京する人も多かった時代です。
そのような中で、劇場や茶屋で上演される短い音楽劇「元曲」が大流行し、『西廂記』はその最も優れた作品の一つとして広く愛されました。
文化的背景
・元曲の普及
庶民にも親しみやすい歌や台詞で構成された原曲は、庶民の娯楽として浸透しました。
・文人の支持
作者自身が科挙合格者であり、教養ある宮廷・都市の聴衆からも高い評価を受けていました。
・戯曲と詩歌の融合
物語のいたるところに差し込まれた詩や詞が、登場人物の心情を繊細に彩っています。
主な登場人物
張生(ちょうせい)・・・ 科挙試験合格を目指し都へ向かう書生。普救寺で崔鶯鶯と恋に落ちる。
・崔鶯鶯(さいおうおう) ・・・名門令嬢。父の招宴で詩を披露し、張生に心を許す。情に厚く、決意も固い。
・皇帝の側近である王将軍・・・鶯鶯の縁談を進めようとするが、最終的に二人を祝福する。
・僧侶・普救寺の住持・・・張生を庇護し、二人の逢引を手助けする。
著書の内容
張生は科挙受験のため、普救寺(府中の名刹)に宿を取る。道中で負傷兵を助けた縁から、寺の僧侶に厚遇され、夜の詩会に潜り込ります。
そこで宴席を飾る鶯鶯の詞章「見面怜清秋」に触れ、張生は一瞬で恋に落ちます。
詩を贈る言葉を口にした瞬間、互いの心が鼓動を刻み始めます。
張生は身分を隠しながら再び鶯鶯の前に姿を現します。
二人は幔帳越しに題詠(テーマを決めて詩を詠む遊戯)を交わし、「折柳令」「孤鴻影」といった曲牌(きょくはい)を通じて心を通わせます。
この場面では、詞章の遣り取りを通じて言葉以上の愛情が描かれ、劇中屈指の美しさを誇っています。
詩会の評判を知られた鶯鶯の母や縁談相手が介入し、二人は引き裂かれそうになります。
張生は故郷へ戻ることを決意し、別れの詞を残します。
「夜風入夢驚相思」といった哀切な文句が、別離の苦しみを生々しく描写しています。
観客には、科挙も恋も捨てがたい葛藤が胸に迫ってきます。
科挙を一時断念した張生は、夜中に密かに寺へ戻ります。
月光の下、二人は再び詞章を交わし、永遠の契りを交わします。
「山長水闊知何處 一片相思寄彩笺」など、未来を誓う言葉が重なり合い、身分を超えた真実の愛が劇的に表出されています。
寺の僧侶や王将軍(鶯鶯の縁談相手でもある側近)が二人を庇護し、父母の強硬も徐々に和らいでいきます。
最終的に縁談は白紙となり、張生は科挙合格を果たしたのち改めて鶯鶯と結婚を許されます。
閉幕の詞では「流水落花春去也 天涯何處覓知音」といった詩句が、愛の勝利と未来への希望を象徴しています。
まとめ
『西廂記』は、身分に翻弄される若い男女の切ない恋路を、美しい詩と華やかな舞台で描き出した名作です。
恋愛の純粋さが社会の制約を乗り越えるドラマは、現代にも共感を呼びます。
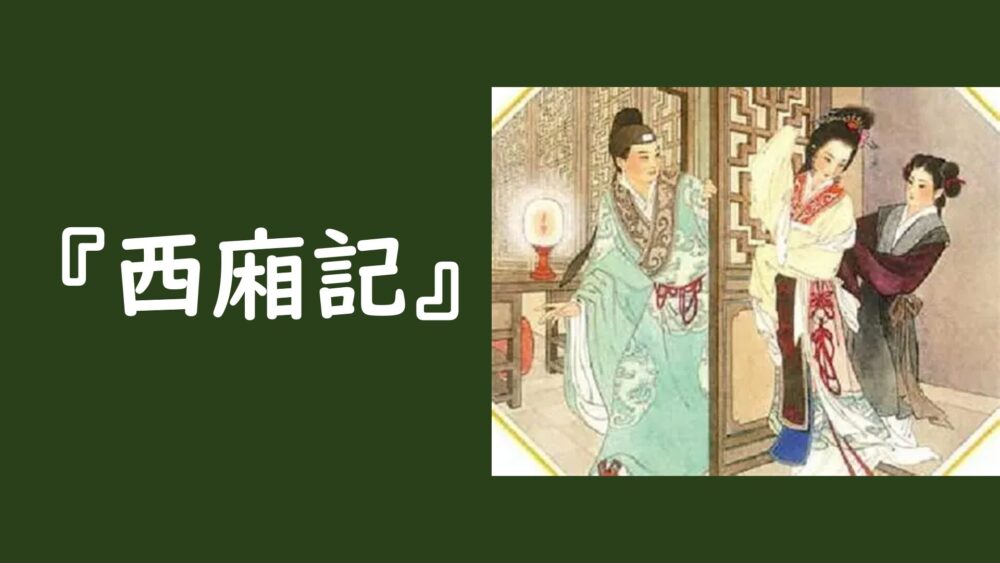
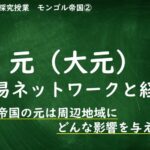
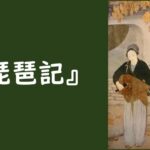
コメント